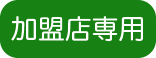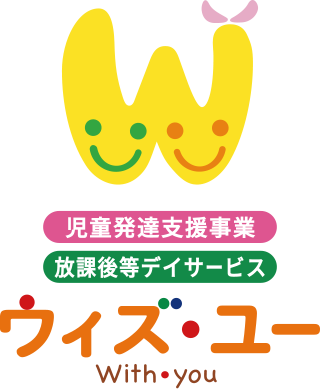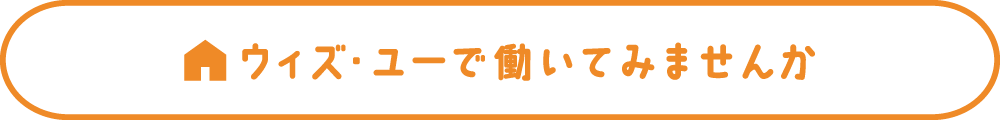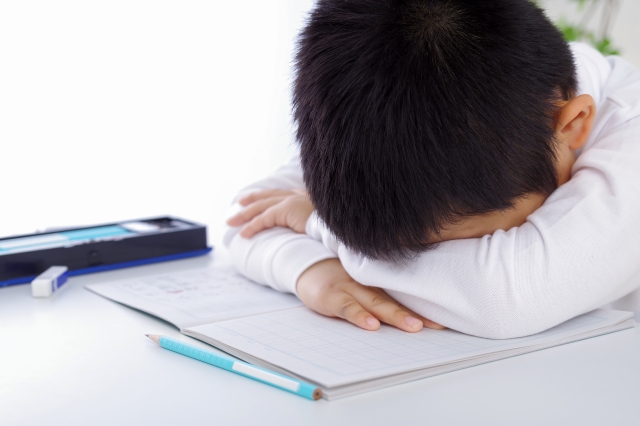
「うちの子、学習障害かも…」
「読み書きが苦手なのは私の遺伝?」
そのような不安や罪悪感を、ひとりで抱え込んでいませんか。
この記事では、学習障害と遺伝に関する科学的な知見をわかりやすく整理し、親の育て方が直接の原因ではないこと、遺伝だけですべてが決まるわけでもないことを説明します。
あわせて、子どもの特性を生かしながら学びを支える具体的な方法も紹介します。読んだあとには、状況を冷静に捉え、お子さんの可能性を前向きにサポートするためのヒントが得られるはずです。
学習障害とは
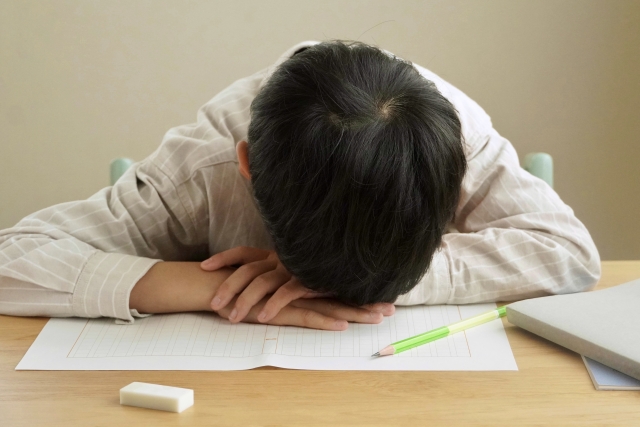
学習障害は、知的な発達に問題がないにもかかわらず、「聞く、話す、読む、書く、計算する」といった特定の能力を学んだり使ったりすることに、著しい困難がある状態を指します。
決して、本人の努力が足りないとか、親御さんの育て方が悪かった、ということではありません。これは、生まれ持った脳の機能の特性によるもので、その子の「個性」の一つと考えることができます。
例えば、「話を聞いて理解するのは得意だけど、文字を読むのはとても苦手」というように、できることとできないことの差がハッキリしているのが大きな特徴です。
まずは「この子が怠けているわけではないんだ」と理解してあげることが、子どもをサポートするための、何よりも大切な第一歩になります。
学習障害の種類
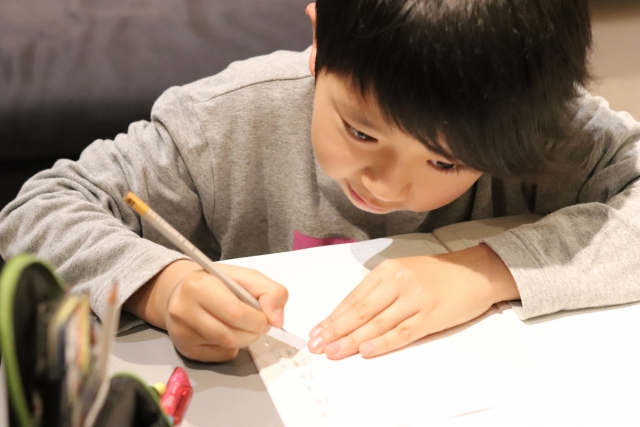
読字障害(ディスレクシア)
読字障害、一般にディスレクシアとも呼ばれるこの特性は、知的な遅れがないのに、文字を読むことに特化して困難が生じる状態のことです。
文字が歪んで見えたり、ぼやけて見えたり、まるで鏡に映したように左右反転して見えてしまうなど、見え方には個人差があります。
そのため、文章をスラスラと目で追うことが難しく、どこを読んでいるのか分からなくなってしまうことも少なくありません。
例えば、以下のような状況が見られます。
- 「め」と「ぬ」、「わ」と「ね」のような形の似た文字を間違える
- 単語の一部の文字を飛ばしたり、勝手に違う文字に置き換えて読んでしまう
- 一生懸命に音読しても、内容が全く頭に入ってこない
本人は真剣に読もうとしているのに、どうしてもスムーズにできないのです。音読が苦手だからといって叱るのではなく、音声教材の活用など、読む以外の学習方法を探してあげることが大切になります。
書字表出障害(ディスグラフィア)
書字表出障害、またはディスグラフィアは、頭の中では言いたいことや文章が思い浮かんでいるのに、それを文字として書き出す作業に大きな困難を伴う特性です。
単に字が汚いというレベルではなく、文字の形や大きさを整えたり、マス目の中にバランス良く収めたりすることが極端に苦手な状態を指します。
まるで、頭の中にある文字の設計図を、うまく手で表現できないようなイメージです。
具体的には、以下のようなサインが見られることがあります。
- 漢字の「へん」と「つくり」のバランスがバラバラになる
- 鏡文字(左右が反転した文字)を書いてしまう
- 文章を書くと、句読点がなかったり、誤字脱字が非常に多くなったりする
黒板の文字をノートに書き写すのにとても時間がかかるのも、この特性が背景にあるかもしれません。
タブレットで写真を撮って記録したり、パソコンでのタイピング入力を試したりと、書くことへの負担を減らす工夫を考えてあげましょう。
算数障害(ディスカリキュリア)
算数障害、またはディスカリキュリアとは、数の概念を理解したり、計算したり、論理的に考えたりすることに限定して、著しい困難が生じる特性です。
国語や社会など他の教科の成績は良いのに、算数だけがどうしても理解できない、というケースも珍しくありません。これは単なる計算ミスが多いとか、算数が嫌いという話ではなく、数の仕組みそのものを捉えるのが難しい状態です。
例えば、以下のような場面でつまずいてしまうことがあります。
- 指を使わないと、簡単な一桁の足し算も難しい
- 繰り上がりや繰り下がりの概念が、何度説明されても理解できない
- 時計の長い針と短い針の関係性が分からず、時間を読むのが苦手
- 買い物の際のお釣りの計算ができない
このような困難さは、本人の頑張りだけでは乗り越えにくいものです。数字の羅列だけでなく、図やイラスト、おはじきのような具体物を使って、数のイメージを視覚的に捉えられるようにサポートしてあげることが効果的です。
学習障害と遺伝の関係

遺伝的要因の影響
学習障害には遺伝が関係する可能性が高いことが、多くの研究で示唆されています。しかし、それをそのまま「自分のせい」と受け止める必要はありません。親子で顔立ちや身長が似るように、学習に関わる脳の働き方の“傾向”が受け継がれやすい、と考えてください。
学習障害は一つの遺伝子で決まるものではなく、複数の遺伝子と環境要因が重なって現れるとされています。遺伝は数ある要因の一つに過ぎない、という点を覚えておきましょう。
遺伝率の研究
「遺伝率」という言葉は、学習障害と遺伝の関わりを数字で示す指標です。ディスレクシアなどの場合、遺伝率はおおよそ40〜60%と報告されています。ここで誤解しやすいのは、この数字が「学習障害の原因の60%が遺伝」という意味ではないことです。
遺伝率は、ある集団の中で見られる学習障害の個人差について、どれだけを遺伝子の違いで説明できるかを示す統計上の割合にすぎません。一卵性双生児(遺伝子が同じ)と二卵性双生児(遺伝子が半分同じ)を比べる研究で、一卵性の方が「二人とも学習障害を持つ確率」が高い──この結果から「遺伝的要因も関係していそうだ」と判断されるわけです。
つまり、遺伝は確かに影響しますが、それだけで決まるわけではありません。環境や経験も大きく関わっていることを、ぜひ覚えておきましょう。
学習障害のその他の原因や背景

親の育て方は直接関係しない
学習障害は、親のしつけや愛情不足が直接の原因になるわけではありません。かつては発達の特性を家庭環境のせいだと誤解する考え方もありましたが、現在の医学や脳科学の研究では、この見方は否定されています。
学習障害は生まれ持った脳の働き方によるもので、その子の個性の一部です。「もっと絵本を読んでいれば」「自分のせいで苦労させているかもしれない」と感じる必要はありません。自分を責める気持ちが過度になると、かえって親子ともに負担が大きくなります。まずは、そうした罪悪感を少しずつ手放し、必要なサポートを考えていくことが大切です。
脳機能の違い
学習障害の背景には、私たちの脳の働き方の違いが関係していることが分かってきています。これは、脳に傷があるとか、どこかが壊れているといった「病気」や「欠陥」ではありません。
例えるなら、コンピューターのOSがWindowsかMacか違うように、脳の中の情報の「配線」や処理の仕方が、多数派の人たちとは少し違う、というイメージです。
そのため、ある情報の処理はとてもスムーズなのに、別の情報の処理には時間がかかるといった、得意・不得意の大きな差が生まれるのです。
fMRI(脳の活動を画像で映し出す装置)などを使った研究では、例えばディスレクシアの人が文字を読むとき、多数派の人とは違う脳の領域が活動している、といったことが観察されています。
これは優劣の問題ではなく、単なる「違い」です。その違いが、時として素晴らしい独創性や発想力を生み出すこともあるのです。
生育環境の影響
学習障害そのものは生まれつきの脳の特性ですが、あとから加わる環境によって症状の出方や子どもの気持ちは大きく変わります。例えば、読み書きが苦手な理由に誰も気づかず「どうして出来ないの?」と叱られ続ければ、子どもは自信をなくし、「どうせ自分はダメなんだ」と学びそのものをあきらめてしまうかもしれません。こうして自己肯定感の低下や学習意欲の喪失、さらには不安やうつなどの二次障害が重なることがあります。
反対に、周囲が早い段階で「この子にはこういう特性がある」と理解し、その子に合った学び方やサポートを用意できれば、子どもは安心して学習に向き合えます。困難を補う工夫や自分の強みを見つけながら、前向きに成長していけるでしょう。環境は学習障害の原因ではありませんが、子どもの力を引き出し、未来を照らす大切なカギになります。
学習障害の遺伝についての誤解

遺伝だから治らない
「遺伝が関わるなら直らないのでは……」と感じるかもしれませんが、学習障害はそもそも風邪やけがのように「治す・治らない」で語るものではありません。重要なのは、特性を理解し、それに合ったサポートで困りごとを軽くし、持っている力を伸ばしていくことです。
視力が弱い人が眼鏡をかければ文字がはっきり見えるようになるのと同じように、読み上げソフトやデジタル教材などの支援ツールを使えば、学習上の困難はぐっと減らせます。実際、世界で活躍している俳優や発明家の中にも学習障害を公表している人が多くいます。大切なのは「治す」ことではなく、特性とうまく付き合いながら、自分の強みを生かしていくことなのです。
遺伝だから親の責任
学習障害に遺伝が関わっていたとしても、それがすべて親の責任になるわけではありません。私たちは誰でも、背の高さや目の形、体質など、さまざまな特徴を親から受け継いでいます。学習に関わる脳の働き方が似るのも、その延長線上にある自然なことです。
今こうして子どものことを心配し、情報を集めているあなたの姿勢こそ、深い愛情の証しです。「自分のせいかもしれない」と責め続ける気持ちは、あなた自身を苦しめるだけでなく、お子さんにも伝わりかねません。まずは罪悪感を手放し、これからできるサポートに目を向けていきましょう。
学習障害は病気
学習障害は「病気」ではなく、生まれつき備わった「特性」の一つです。
病気は治療して元の状態に戻すイメージがありますが、特性はその人を形づくる個性です。例えば、絵が得意な子もいれば、人前で話すのが得意な子もいます。同じように、文字を読むことより耳で聞くほうが得意な子がいても不思議ではありません。
左利きの人を病気だとは言わないのと同じで、学習障害も脳の情報処理の仕組みが多数派と少し違うだけ―いわば「脳の多様性(ニューロダイバーシティ)」の一例と考えられています。
「病気」という言葉をあてはめると、どうしても「治さなければならない欠点」のように映ります。しかし、「その子ならではのユニークな個性」と見直せば、子どもへのまなざしも支援の方法も、大きく変わっていくはずです。
学習障害を持つ子どものサポート方法

子どもの特性を理解する
子どもを支えるうえで、最初にして最も大切なのは「なぜできないのか」と責めるのではなく、「何に、どう困っているのか」を理解しようとする姿勢です。
「どうしてわからないの?」と感情的になりそうなときこそ、いったん立ち止まって想像してみてください。もし文字が二重にぶれて見えたり、頭の中の言葉がうまく手に伝わらなかったりしたら-。子どもは、そのような世界で懸命にがんばっているのかもしれません。
困りごとを客観的に捉えるには、医療機関や教育支援センターでWISCなどの心理検査(アセスメント)を受ける方法が有効です。検査から得意・不得意の傾向が見え、具体的な支援策を立てやすくなります。
そして何より、親であるあなたが子どもの最大の理解者になることです。それが子どもにとって、何にも替えがたい「心の安全基地」になります。
失敗を恐れず挑戦できる環境をつくる
学習障害のある子どもは、学校生活の中で、他の子どもよりも「できない」「失敗した」という悔しい経験を多く積み重ねてきている可能性があります。
そのため、自分に自信が持てず、新しいことに挑戦するのを怖がってしまうことも少なくありません。だからこそ、家庭では「失敗しても大丈夫だよ」というメッセージを伝え続けてあげることが、何よりも大切になります。
大切なのは、結果をほめることではありません。100点が取れたかどうかではなく、「難しい問題にチャレンジしようとした勇気」や「最後まで諦めずに取り組んだ姿勢」を、具体的に言葉にしてほめてあげましょう。
「字は上手に書けなかったけど、昨日は5分で嫌になったのに、今日は10分も机に向かえたね!すごい!」こんな風に、過去の本人と比べて、ほんの少しの成長を見つけてあげるのがコツです。
家庭が「どんな自分でも受け入れてもらえる安全な場所」であるという安心感が、子どもが再び挑戦するためのエネルギーを充電してくれるのです。
本人の得意なことや興味を伸ばす
私たちはつい、子どもの「できないこと」ばかりに目を向けて、それをどうにか克服させようと必死になりがちです。
もちろん、苦手なことへのサポートは大切ですが、それと同じくらい、いえ、それ以上に重要なのが、本人が「得意なこと」や「大好きなこと」を見つけ、それを思いっきり伸ばしてあげることです。
子どもには、必ず何か「キラリと光るもの」があるはずです。その「好き」や「得意」に没頭している時間は、子どもの自己肯定感をぐんぐん育ててくれます。
「自分にも、人よりできることがあるんだ!」という自信は、生きていく上での大きな武器になります。そして不思議なことに、一つのことで得た自信は、苦手なことに取り組む意欲にも繋がっていくのです。苦手なことの穴埋めばかりに時間を使うのではなく、得意なことを伸ばして、自信という大きな器を育ててあげましょう。
読み書き以外のコミュニケーション手段を大切にする
文字の読み書きに困難があると、自分の気持ちや考えを表現する手段が限られてしまい、もどかしい思いをしているかもしれません。だからこそ、読み書きというツールだけにこだわらず、さまざまなコミュニケーション手段を大切にしてあげてください。
一番基本となるのは、「話す」そして「聞く」という対話です。子どもが、たどたどしくても一生懸命に話そうとしているときは、忙しくても少しだけ手を止めて、目を見てじっくりと耳を傾けてあげましょう。相槌を打ちながら聞いてもらえるだけで、子どもは「自分の気持ちを分かってもらえた」と深く安心することができます。
言葉でうまく言えないなら、絵に描いてもらったり、粘土で作ってもらったりするのも素晴らしい方法です。テストの点数や文字の上手さといった表面的なことではなく、その子の内側にある心と心を通わせることが大切です。
まとめ

学習障害と遺伝の関係について不安や「自分のせいかも」という気持ちを抱いていたとしても、原因は親の育て方ではなく、生まれつきの脳の特性であること、遺伝は数ある要素のひとつにすぎないことをご理解いただけたでしょうか。
大切なのは過去を振り返って悩むことではなく、目の前のお子さんとこれからの成長に目を向けることです。まずは特性をありのまま受け止め、日常の中で「何に困っているのか」「どうすれば学びやすくなるのか」を一緒に考えてみてください。
支援にあたっては、学校や教育支援センター、専門医、同じ悩みを共有する保護者の会など、頼れる場所が数多くあります。ひとりで抱え込まず、周囲の力を借りながら、子どもの可能性を伸ばす方法を探していきましょう。
この記事が、気持ちを少しでも軽くし、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。