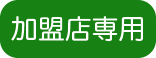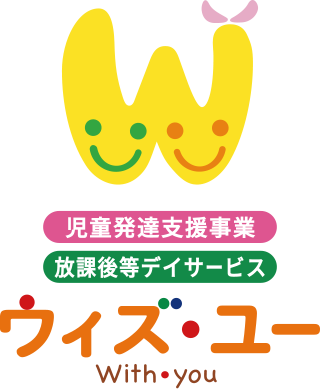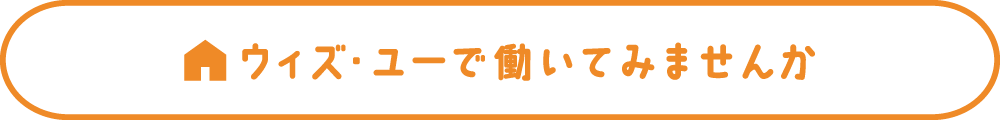「うちの子、歩くときにつま先立ちばかりしている…」
「普通のクセなのか、それとも何か発達の問題かしら?」
そんな不安を抱えていませんか?
発達障害のあるお子さんは、感覚の偏りや筋力のバランスの問題によって、独特な歩き方が見られることがあります。適切な理解とサポートを行うことで、子どもがより楽に、そして安全に生活するための大きな手助けになるはずです。
そこで、この記事では発達障害における歩き方の特徴や、具体的な改善策について詳しく解説していきます。気になる歩行のクセをどうすればいいか知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
発達障害における歩き方の特徴

つま先歩き
つま先歩きは、自閉症スペクトラム症(ASD)の早期発見につながるケースもあり、1〜2歳頃によく見られる行動です。 また、つま先周辺に感覚過敏が集中している子どもの場合、つま先を浮かせてかかとで歩くこともあります。
この状態が続くと、ふくらはぎの筋肉が硬くなりやすく、転倒のリスクも高まります。
発達障害の場合、感覚過敏で足の裏に刺激が当たるのを嫌がる子が多く、つま先に重心を置いて歩く傾向があるとも考えられています。
また、感覚面の課題だけでなく、運動協調性の問題や習慣化も影響します。つま先歩きが長期化すると歩行バランスに偏りが出るため、専門家に相談しながら適切な対応を取ることが大切です。
すり足歩行
すり足歩行は、足を床にこすりつけるようにして歩く歩き方です。姿勢の崩れや運動コントロールの難しさが表面化しているケースが多いといわれてます。足を引きずると靴底が偏ってすり減りやすく、転びやすい点も無視できません。
すり足歩行が習慣化すると、骨盤まわりの筋肉が十分に使われず、腰痛や疲れやすさの原因になる場合もあるので注意が必要です。発達障害では、空間認知がうまくいかず自分の身体位置を正確に把握しづらいことが影響することもあります。
歩幅を意識的に大きくしたり、足を高く上げる練習を取り入れることで、重心移動をスムーズにできる可能性があります。自宅や学校で、数歩だけ「膝をしっかり上げるウォーキング」を練習するだけでも、すり足の改善に役立ちます。
ペンギン歩き
左右に大きく揺れながら、外側に足を向けて歩く様子をペンギン歩きと呼ぶことがあります。ももや股関節の可動域に偏りがあると、足先が外側に開きやすく、バランスを取るために左右へ揺れてしまうのです。
この歩き方は見た目でわかりやすく、「何か困っているのでは」と周囲から心配されやすい特徴もあります。発達障害の子どもは筋力のバランスがアンバランスなことや感覚過敏で足の向きを変えていることもあります。
ペンギン歩きのまま成長すると、足首や膝の負担が偏る場合があり、将来的な関節トラブルのリスクが増すと考えられています。歩くときに骨盤周囲の筋肉を積極的に使う練習や、正面に足を向けるストレッチなどが効果的です。
その他の特徴的な歩き方
上記以外にも、膝を曲げたまま小走りのように進むパターンや、左右の足を交互に運ぶのが極端に遅い歩き方などさまざまです。
視線の使い方や身体バランスの取り方に偏りがあって、真っ直ぐ前を向いて歩けないケースもあります。
注意すべき点は、どの特徴も日常生活に支障をきたす可能性があることです。
特に衝動性が強い子は、周囲をよく見ずに歩くことで対人トラブルや怪我につながるリスクもあります。
短距離だと大きな問題がなくても、長距離や運動会など集団での活動時に目立つことも多いです。
歩き方の違いは見た目だけではなく、身体の左右差や協調運動の遅れを示している場合もあるので、気になったら早めのケアが重要です。
発達障害の種類別に歩き方の特徴に違いはあるか?
発達障害には、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、様々な種類があります。歩き方の特徴に、発達障害の種類による明確な違いは見られません。
一例としては、ASDの子どもには感覚過敏の影響で床からの刺激を嫌がりやすく、つま先歩きが多いとされる傾向があります。ADHDの子どもの場合、落ち着きのなさや衝動性が先行して、走るように小走りで移動したり、バタバタ歩きになりがちです。
LDの子どもでは運動協調性の問題が目立つケースがあり、足の運びがぎこちなくなる場合があります。
とはいえ、これらはあくまで典型的なパターンで、必ずしも全員に当てはまるわけではありません。
歩き方だけで正確な診断を行うのは難しいですが、気になる特徴があれば複数の専門機関で評価を受けると安心です。
歩き方の特徴から発達障害の可能性を判断できる?

歩き方の特徴だけを見て「発達障害かどうか」を断定するのは困難だと考えられています。つま先立ちやつま先歩きは、子どもの成長過程で自然に見られる動作の一つでもあります。
周囲から見て「いつもかかとをつけない」「バランスを極端に崩す」「本人が痛みを訴える」などの要素があれば、医療機関やリハビリ専門家に相談して原因を探ることが大切です。
また、発達障害は歩き方だけでなく、コミュニケーションや学習面でも特徴が見られることが多いです。そのため、複数の視点で総合的に判断を行う必要があります。
「どうしてこれほど歩き方が違うのか」と感じるようなら、家庭や学校での様子を観察し、気になった点をメモすることが有益です。
早めに気づいて対応を始めるほど、子どもに合わせたサポートを見つけやすくなります。
歩き方の問題が子どもの日常生活に与える影響

転倒のリスク増加
つま先歩きやすり足など、重心の移動や足の上げ方に偏りがあると、つまずきやすくなります。足を地面にこすったり、かかとが接地しないままで歩くと、小さな段差や床のわずかな凹凸でも転倒につながりやすいです。
転倒は膝や頭を打つリスクが高いので、運動能力の向上以前にまず怪我を予防する視点が重要です。特に注意力が散漫になりやすい子は、周囲の状況を把握せずに歩いてしまうことが多く、転び方が大きくなる場合もあります。
練習や訓練を行う前に、安全対策として室内の段差や障害物を減らすのも効果的です。屋外では、凸凹の道や階段を歩くときに手をつないだり、転倒を防ぐための声かけをするなど工夫しましょう。
こうした地道な対策が続くと、子ども自身の歩く自信も育っていきます。
運動能力の制限
歩き方に独特のクセがあると、体全体をバランスよく動かすのが難しくなりやすいです。
例えば、つま先歩きが習慣になると、ジャンプやスキップなどの動きに苦手意識が出てきます。一部の筋肉だけが酷使されている状態だと、運動会や体育の授業で力を発揮しにくく、本人が自信を失う原因にもなるのです。
また、足の動きと手の動きを連動させる全身運動が苦手になり、チームスポーツなどで苦労しやすいことがあります。
このような運動のしづらさは、発達障害特有の運動協調性の弱さや感覚過敏とも関連します。小さな成功体験を積み重ねると、「走るのって楽しい」と感じるきっかけにもなるため、子どもの興味に合わせた体を動かす遊びを取り入れるのが有効です。
持続的にサポートすれば、本人の運動面での能力も少しずつ伸びていきます。
足の痛みや変形
偏った歩き方が長く続くと、足や脚全体の骨や筋肉の成長に影響を与えることがあります。
例えば、つま先歩きが常態化すると足裏の膜やアキレス腱に負荷がかかり、痛みを生じやすくなります。
さらに、膝や腰への負担も増して姿勢が崩れやすく、筋肉や関節のバランスが乱れるリスクが高いです。
成長期の骨は柔軟ですが、無理な方向に圧力がかかると足の骨格が変形する可能性もあります。特に内反足(足首が内側に傾く状態)や外反足(足首が外側に傾く状態)が進むと、痛みだけでなく靴選びにも苦労するようになります。
こうした痛みや変形は早めに対処しないと、歩くこと自体が辛くなり、子どもの活動意欲を削ぎかねません。痛みを訴えるときは、整形外科などを受診し、適切な治療や装具の使用を検討すると良いでしょう。
感覚過敏
発達障害の子どもは感覚過敏を抱えていることが多く、足に触れるわずかな刺激でも苦痛に感じる場合があります。床の硬さや靴の生地が気になってしまい、つま先に重心を置いて楽な歩き方を模索する子もいます。
このように身体を守るために独特の歩き方が身についた結果、筋肉や関節に余計な負担がかかるパターンも少なくありません。感覚過敏を軽減する工夫として、刺激を吸収しやすい靴やインソールを選ぶ、靴下の素材を変えるなどの方法があります。
歩行練習と平行して、苦手な感覚を少しずつ慣らしていく方法も試してみましょう。感覚面の困難は「わがまま」ではなく、本当に苦しい場合があるので、子どもの訴えをしっかり受け止める姿勢が大切です。
安心できる対策を取り入れることで、歩くことへの抵抗感が減り、姿勢の改善につながりやすくなります。
発達障害による歩き方の変化

子どもの歩き方が変わる理由
成長とともに身体バランスや骨格も変化しますが、発達障害の子どもはこれらの変化に適応しづらい側面があります。小学生になると身長や体重が増え、重心位置も変わりますが、うまく身体をコントロールできないと歩き方がぎこちなくなりやすいです。
社会に出る機会が増えると周囲との比較や自己意識が高まり、逆に無理に普通の歩き方をしようとして不自然な動きが強まることもあります。感覚面の変化や心理的ストレスによって、同じ子でも学年が上がるたびに歩き方の特徴が出たり消えたりする可能性があるでしょう。
特定の環境下だけで見られる歩行パターンもあり、家と学校で歩き方が違うケースも見られます。こうした揺れ動く要因を踏まえて、どのような状況で歩き方が顕著になるか観察するのが大切です。
なるべく早めに専門家と連携し、子どもの成長ステージに合わせた指導を行うことで良い方向に変化しやすくなります。
大人における独特な歩き方の事例
発達障害は子どもだけでなく、大人にも継続して影響を及ぼします。自閉スペクトラム症の人は、感覚過敏の特性が残ったまま成長すると、自分にとって心地よい歩き方を無意識に続けることがあります。
結果として、社会人になってもつま先歩きが抜けなかったり、一歩一歩を非常に小刻みに踏み出すケースもあります。
外見上は「少し姿勢が悪いかな?」程度に見えるため、大人になって初めて支援を受けるケースも少なくありません。日々の通勤や立ち仕事が重なれば、膝や腰に痛みを抱えてからようやく問題を自覚する人もいます。
専門家に相談して靴を調整したり、歩行指導を受けると足への負担が軽減され、体全体が楽になる可能性があります。社会生活が長いからこそ、正しい歩行を学び直す意義は大きいといえるでしょう。
発達障害の子どもの歩き方を改善する方法

日常生活での具体的なアプローチ
普段の生活の中で簡単に取り入れられる工夫が、歩き方改善の第一歩になります。
例えば、お風呂上がりや朝の支度前に足首のストレッチを行い、柔軟性を高める習慣をつけるのもおすすめです。家の中に短い距離でも「かかとから着地して歩く練習コース」をつくり、大人が手本を見せながら一緒に歩く方法も効果があります。
靴を選ぶ際には、かかとや土踏まずのホールド感がしっかりあり、子どもの足に合ったものを選びましょう。
インソールの活用で、つま先歩きや足の傾きを修正できることもあります。ただし、嫌がる子もいるので、無理に矯正するより「少しずつ慣らしていく」ほうが続けやすいです。
子ども自身が自分の歩き方を意識できるよう、動画で撮影して見せるのも有効です。
効果的な運動療法と遊び
歩き方改善には、子どもが楽しめる運動や遊びを通して取り組むことが大切です。
バランスボールや平均台などを使った遊びは、体幹の安定と足の使い方の意識付けに役立ちます。つま先やかかとだけで立ってみる「片足立ちゲーム」も、筋力やバランス感覚を養いやすい方法です。
屋外での遊びなら、砂場での足踏みや坂道を登り降りするなど、自然に足を大きく動かす機会を設けましょう。リズムに合わせて足を動かすダンスやリトミックは、運動協調性を高めつつ楽しく身体を動かせるのでおすすめです。
継続して遊びと運動を組み合わせることで、歩くときにも身体をコントロールする感覚が身についてきます。専門家やリハビリスタッフと相談し、子どもの興味に合わせたプログラムを取り入れると長続きしやすいです。
歩き方の問題を抱える子どもへのサポート方法

家庭でのサポート
保護者ができるサポートは、子どもの生活習慣を細かく見直すところから始まります。
座り姿勢を見直すだけで足の筋力に変化が出ることがあります。食卓の椅子の高さを調整し、足裏がきちんと床につくようにしたり、背中が丸まらないようクッションを使うのも一手です。
歩き方を責めたり、無理に矯正しようとするのではなく、まず「どうしてそんな歩き方が楽なのか」を一緒に考えてみてください。気持ちに寄り添うことで、子ども自身が意欲的に改善に取り組みやすくなります。
普段の生活の中に、歩行練習を意識した遊びや運動を織り交ぜるだけでも大きな成果が期待できます。
「今日はかかとを少し意識できたね」など小さな変化をほめてあげることで、子どもの自信を積み重ねていきましょう。
専門機関との連携
理学療法士や作業療法士など、運動や身体機能の専門家に相談することをおすすめします。
整形外科で足の骨格や関節の状態を確認し、必要に応じて装具を作ってもらうケースもあります。歩き方に限らず、言語面や認知面の課題もあれば、発達支援センターや児童精神科のサポートを受けることを検討しましょう。
特別支援教育コーディネーターやスクールカウンセラーに相談し、学校での配慮を得ることも大切です。
専門機関と連携すると、家と学校の両面で対策を講じられるので、子どもの成長に合わせたサポートを計画的に進めやすくなります。
医療と教育をつなぐ役割を持つ支援者は多いので、紹介を受けながら必要なサービスを組み合わせてください。大切なのは、子どもが安心して学んだり生活できる環境を整えることで、歩き方の改善も自然に進みやすくなる点です。
まとめ

発達障害の子どもたちは、感覚や運動の特性が歩き方に出やすいですが、それがすべてマイナスというわけではありません。一見目立つ歩行パターンがあっても、正しいサポートや運動療法を継続すれば、バランスの良い体の使い方を身に付けられます。
家庭での小さな工夫から、専門家による指導まで、多彩な方法を組み合わせてサポートすることが重要です。
歩き方の問題は、単なる癖だけでなく感覚過敏や筋力アンバランスなど、多角的な原因が絡んでいる可能性があります。だからこそ、保護者や教育者が早めに気づき、専門機関と連携しながら子どもにあったサポートを選択することが大切です。
本人の性格や興味を尊重しつつ、遊びや運動を楽しみながら改善につなげていけば、子どもにとっての生活の質は必ず向上します。家族や学校、地域の支援者が協力することで、子どもの可能性を広げていきましょう。